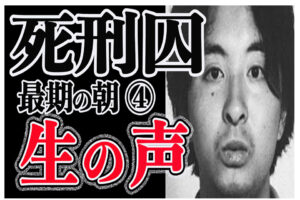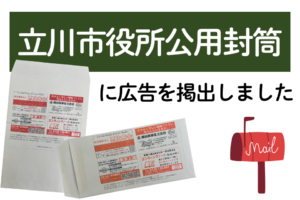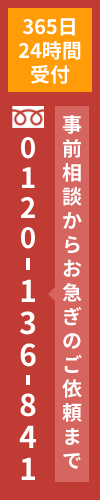お葬式中に…相続争いが始まっていたら?・・・・お葬式の後、みんなで冷静に話し合えばいい”——そう思っていませんか?でも 現実はそう甘くはありません。喪主の決定をめぐる 骨肉の争いや、親の遺影写真の前で 声を荒げ 口喧嘩する兄弟など、そんな修羅場を、私たち葬儀社は何度も見てきました。今回は、葬儀社だからこそ見える“争族のリアル”をお伝えします。
葬儀は、大切な人との最後のお別れ。けれど、そこで本当に“家族の別れ”にもなってしまうことがあるのです。
——それが、“争続”です。争族で人生壊したくない方、必見です。

葬儀社だからこそ見えた!親族間の相続争い
葬儀社だからこそ見えた親族感の相続争いは 実は、お葬式前から始まっています。兄弟・姉妹で会話がソワソワ・・・遺産の話でギクシャク・・・皆さんも そんな経験ありませんか?
原因は何だと思いますか?コミュニケーション不足?
結論から言います。それは たった1つです。
遺言書が無いと、こうなるんです。争族…本当にあった怖い話しを ご紹介していきます。
遺言書が無い家庭
遺言書がない家庭では、親が亡くなる前から 相続への不安がくすぶり、葬儀の場ですら「遺産の話」でもめるケースが結構・・・あります。
葬儀社として、私たちが実際に見てきた【争族トラブル・悲劇】をお伝えしていきます。
まず基本からです。なぜ遺言書がないと、お葬式前から争いが起きるのか?「お金の不安」がすぐに表面化します。例えば 葬儀費用は誰が払うのか?誰が建て替えるのか?とか、墓の管理費、自宅の維持費などは 誰が負担するのか?➡️決まっていない。
また 特定の子が主導権を握りたがる。親と同居していた子が「自分が相続するのは当然」と主張し始めたり、または長男・長女だからと言って喪主をするのは当たり前と主張したりします。
更に「遺品の行方ですぐに対立」します。形見や仏壇、ジュエリー、わずかな現金ですら「誰のものか」でもめるのです。
喪主は俺だ!お葬式の打ち合わせが 修羅場に変わる瞬間
それは、お父様が亡くなって…まだ1日も経っていない頃でした。ご家族が集まり、弊社のスタッフと 葬儀の打ち合わせが始まります。葬儀の日取り、会場、祭壇の種類…などなど。私たちは粛々と話を進めようとしていました。スタッフが 説明を始めようとしたその時、長男が口を開きました。
「俺が長男だから、喪主は当然俺がやる。そういうもんだろ?」語気を強める兄・・・。
対して、次男がすぐに反論しました。
「でも最後まで親の介護・面倒見てたのは、俺と嫁だぞ!」と・・・。
突然の対立に 周りの親族も戸惑っていまいました。次第に声が大きくなり、スタッフが間に入っても話は平行線のままでした。母親や他の兄弟は沈黙し、場の空気は凍りついたままで、お葬式の打ち合わせは一時中断になってしまいました。

冷静に考えれば、どちらも悪気があったわけではありません。お兄さんは家族と先祖を代表する立場としての責任感から。弟さんは自分が親を見てきた・準備を担ってきたという自負から。それぞれが「自分がやるものだ」と思い込んでいただけ。でも、この“思い込み”のズレが、二人のプライドや感情に火をつけてしまったのです。
お互い「なんで 今さらそんなことを言うんだ!」という気持ちになってしまい、話し合ってこなかった分、口論に発展してしまいました。言い換えれば、『話し合ったことがないのに 自分の中だけで 当たり前にしていた』という、この認識ギャップこそが、今回の争いの根本原因になってしまったです。「私たち葬儀社は、こうした現場を何度も見ています。
“お葬式前から始まる相続トラブル”は、決して他人事ではありません。
私は毎回、思うのです。
遺言書がない。話し合いも していない。それがどれほど、家族の絆を壊してしまうか——それから 喪主というのは「名誉」でも「責任」でもあります。どちらがやるかは、“血筋”だけで決める時代でもありませんし、また「香典返しや お礼カードには 通常は、喪主名義で「ご挨拶文(礼状)」が入ります。そのため、会社や上司が香典を出した場合、喪主としての名前があれば
“ああ、本人が代表して対応しているんだな”と理解されやすい、という面は 確かにあります。親が生前に意思を示しておくべき重要なことの ひとつとして「喪主を誰が務めるか」についても、親が伝えておくべきだと私は思います。何故なら、親が伝えておくと・・・
①家族間の揉めごとを防げます。
→ 長男・次男、嫁、親族…立場が違えばそれぞれ主張も違います。
→ 親の意思があれば、明確な“基準”になるからです。
②葬儀の方向性がブレにくくなる。
→ 立派にやりたい人・質素でいい人、それぞれの考え方が違う中で「○○に任せる」と言われていれば、スムーズに進行できる。
③喪主=代表として“責任”を引き受ける覚悟が持てる
→ 親に任されたという“納得感”があれば、他の家族も従いやすい。というメリットがあります。

親の介護をめぐる恨みが 相続に直結
亡くなった母親の介護を長女が担っていたが、他の兄弟はほとんどノータッチでした。 遺産の分け方について何も取り決めが無く、遺言書もありませんでした。葬儀が終わり、控え室での会話でした。親戚も帰ったあと、遺産分割の話が自然と始まりました。
兄(長男):「じゃあ、遺産はきょうだい3人で平等に分けようか」
介護者の長女:「え?…ちょっと待って。10年間、介護したのは私一人よ。時間もお金も使ったの。
それを“平等”って…納得できない。」

💬妹(次女):「でも、お母さんは“3人で分けて”って言ってたじゃない」
💬長女:「それはあなたたちが 介護から逃げてたから言わせたんでしょ…」
ここから、積もり積もった感情が一気に噴き出し、口論に発展。空気はピリピリ、スタッフも近寄れない状況に。

🔹なぜこんなことになるのでしょうか?
「介護した苦労=報われるべき」という感情・・・
「兄弟なんだから平等が当然」という感覚
でも、事前に何の話し合いもしていなかったため、お互いの「正義」が ぶつかってしまったのです。
「10年も介護したのに、“平等に分ける”って納得いかない…」
「あの人は親の面倒なんて見なかったのに、同じ額もらうなんてずるい」
こういう 気持ちの不満って、とてもよくあるし、自然な感情なんだと思うのです。

🔸専門的な視点から見ると
実は「介護した人に多めに相続させる」ことは、法律では基本的に考慮されません。 ※ただし「寄与分」という制度はあるが、かなり限定的で手続きが難しいです。
つまり——
💥 介護してもしなくても、遺言がなければ原則“平等”となるのです。
→ そこに感情の不公平感が生まれることで、私は“争族”になると思うのです。では、防ぐにはどうすれば?いいのでしょうか?これは私は 親にとっても非常にメリットがあることと思います。
①親が生前に 遺言を作成すること(寄与分を考慮した内容)
②親が兄弟間で 介護に関する分担や 将来の約束を文書にしておく。
「介護を誰が見るか」を遺言書や書き残しにして 事前に知らせておくことは、親自身にとっても大きなメリットがあります。多くの人が「子どもたちがうまくやってくれるだろう」と思っていますが、実際は話し合いのないまま 介護が始まると、きょうだい間の不満・誤解・負担の偏りが噴き出すことが少なくありません。遺言書に付け加える「付言事項」(ふげんじこう)で、
「○○にはこれまで いろいろしてもらったから 感謝している」
「できればこれからもお願いしたい」
などの想いを添えると、心の支えになります。実はこの「気持ちの一文」が、きょうだい間の対立を防ぐ一番の鍵になることも多いんです。
介護のことって、“なるようになる”って思ってませんか?でも、実際は“なるようにならずに、もめる”んです。だからこそ、元気なうちに——“誰にお願いしたいか” “どんなふうに過ごしたいか”
それを親の口から伝えて 遺言書を残すだけで 未来は大きく変わります。

本日のまとめ
大切な人を見送る、その瞬間。本当なら、家族がひとつになって、“ありがとう”を伝える時間のはずなのに…
「遺影の前で声を荒げる兄弟。」
「火葬場に向かう車の中で飛び交う“通帳はどこ?”の言葉。」
母の介護をめぐって、葬儀後にこぼれる涙と怒り…。私たちは、そんな現場を、いくつも見てきました。
どうしてこんなことが起きるのか・・・それは、家族の誰も“話してこなかった”からなんです。
“長男だから当然だと思ってた”
“10年も介護したのに…”
“まさかこんなことで 揉めるなんて”
どれも、どのご家庭にも起こり得ること。そしてその根っこにあるのは・・・ただ一つ、遺言書がなかったという事実。
遺言書って、“お金の話”だけじゃありません。そこには、“誰に託したいか” “誰に感謝しているか”・・・心のメッセージが込められるんです。
その一枚の紙が、親を看取った子どもたちの関係を 守ってくれる。
家族が“お父さんは、ちゃんと考えてくれてたんだね”って 微笑み合える日が、きっと来る。だから今こそ、声をかけてみてください。
“うちも遺言書のこと、一度話してみない?”って。
その一言が、未来の争いを止めるかもしれません。家族の絆を守る、やさしい準備なのです。

 0120-136-841
0120-136-841