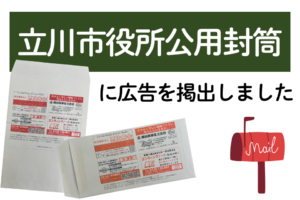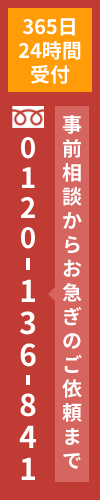「お盆って、結局なにをする日なの?」
迎え火・送り火・盆踊り……言葉は知っていても、由来も意味もよく分からない──そんな声を毎年聞きます。
もし“やり方”を間違えると、せっかく帰って来たご先祖さまが迷子になるかもしれません。今日は葬祭ディレクター目線で、準備・当日の流れ・最新トレンドまでを丸ごと解説。最後まで見ると、今年のお盆が3倍楽しく、心に残る時間もできます。

目 次
- お盆の由来3行解説
- お盆1日の流れ
- 盆踊りの秘密ベスト5
- 知らないと損するマナーQ&A
- 2025年最新トレンド&経済効果
- 忘れがちな“送り火”の意味
- お彼岸とお盆、何が違う?
- まとめ

1. お盆の由来3行解説
お盆は正式には盂蘭盆会と書きます。盂蘭盆会の“ウラボン”はサンスクリット語 Ullambana が転じた言葉で、“逆さ吊りの苦しみを救う”とも、“助け起こす”とも訳される──諸説ありますが、いずれも『困窮する霊を供養して救う』という意味合いで、お釈迦様と目連尊者(もくれん そんじゃ)の逸話がルーツです。「母を餓鬼道から救うには僧侶への供養が最善」と教わり、7月15日に大供養をしたのが始まり。その後、祖霊を招き送る年中行事へと形を変え、日本独自の“帰省シーズン”になりました。子どもには「天国からおじいちゃんが帰ってくるホームステイ期間」と説明するとすっと伝わります。

2. お盆1日の流れ
迎え火→精霊棚(しょうりょうだな)→墓参→送り火――この4ステップが基本。

「時刻は午後四時半。まずは“迎え火セット”を玄関先に並べます。
オガラ五本、ロウソク二本、線香、そしてマッチ。
ここで忘れがちなのが耐熱皿。火皿代わりに置くと安心です。」
「白い布を広げて――はい、精霊棚の土台が完成。
写真と位牌を真ん中に。
「午後五時、いよいよ迎え火。
オガラを“井”の字に組んで、ロウソクで着火。
立ち上る煙が、ご先祖さまへの“道しるべ”です。
炎が大き過ぎたら、指でそっと水をひと差し――火は“灯す”が基本、燃やし尽くさない。」
「火を迎えたら、夕食前に精霊棚を仕上げましょう。
“プリン、せんべい、缶ビール”――故人の“推しメニュー”を三品までを目安に。「午後七時。夕食をとりながら、一人ひとつ“思い出エピソード”をシェア。
スマホのスライドショーで昔の写真を流すと、語らいが自然に弾みます。
ここで、BGMは軽い和太鼓に変えると“夏祭り感”マシマシです。」
「翌朝七時。まだ涼しい時間に墓参へ。
花筒の水を入れ替え、榊は斜め四十五度で左右対称に活けるのが写真映えのコツ。
線香は三本、扇状に寝かせて胸の高さで合掌。
朝八時までに済ませると、花も枯れにくく人も少なめです。」
「そして最終夜、午後八時――送り火。
迎え火と同じ場所で、もう一度オガラに点火します。
炎が落ち着いたら塩をひとつまみ、『安全運転で帰ってね』。
「“迎え火・精霊棚・墓参・送り火”――
この4ステップがそろって、ようやくお盆はワンセット。
忘れないコツは、Googleカレンダーで毎年リマインダーを設定。
通知音を“虫の声”にすれば、スマホからも夏の気配が届きます。」
3. 盆踊りの秘密ベスト5
①そもそも盆踊りは踊り念仏で、足を踏み鳴らし先祖や悪霊を鎮める“供養の行”で、踊りの振動が徳を届けるといわれ、学術的には「祖霊を慰めて送り返す」と言われています。
②東京音頭は昭和初期に生まれ、その後プロ野球で応援歌に採用されました。
③ 昭和の高度成長期、和太鼓+エレキギターの編成が登場。今聴くと逆に新鮮です。
④ 令和は“クラブ化”! DJ盆踊り in 渋谷では、やぐらの代わりにDJブースが鎮座。SNS映え狙いの若年層やインバウンド客に人気です。
⑤ 動きは地方色満載。徳島阿波踊りの掛け声は「ヤットサー」ですが、踊りの節(リズムパターン)を**“よしこの節”ブシ**と呼ぶます。岐阜・郡上おどりは腕を大きく回す“風を切る”動きで知られています。現地に行けない人はYouTubeのライブ配信を観ながら手だけ真似してもOKです。
★今日話したくなる豆知識:盆踊りの輪は左回りが多く。“太陽の運行と同じ向きで縁起がいいから”と言われています。

4. 知らないと損するマナーQ&A
Q. 浴衣でお寺に行ってもいい?
A. カジュアルなお墓参りや盆踊りに立ち寄る程度なら、紺や白など落ち着いた浴衣ですが、読経・焼香を伴う正式な法要や直会がある場合は 略喪服(ダークカラーのスーツ/ワンピース) が無難です。
Q. ペットボトルのお茶を供えていい?
A. ラベルを外してコップに注げば丁寧ですが、お参りが終わったら必ず下げて持ち帰るのが基本マナーです。缶や瓶をそのまま置き去りにすると動物被害やゴミ問題の原因になります。。
Q. 迎え火の時間がズレたら?
A. 夕方17〜20時頃なら地域差の範囲内。多少前後しても「迎え損ねた!?」と慌てるより、心を込めて灯すほうが大切です。
私自身、雨で迎え火を焚けずロウソク一本で代用した年がありますが、「煙より気持ち」と祖母が笑ってくれました。マナーは形式と心のバランスが大事――そんなふうに覚えておくと安心です。

5. 2025年最新トレンド&経済効果
2023年の徳島阿波おどりは2日間で約25億円の経済波及効果を生みました。宿泊・飲食・交通すべてが地域にお金を巡らせ、400人分の雇用も創出です。
渋谷のDJ盆踊りは、クラフトビールやNFT御朱印まで販売し、若年層とインバウンド客を呼び込む“夜間経済”の星。
自治体はふるさと納税返礼に「帰省サポートチケット」を出す動きもあり、2025 年は“お盆テック元年”とも呼ばれるほど、デジタル化が加速しています。伝統行事が最新ビジネスと混ざる様子は、まさに「ご先祖 × Z世代」のコラボですね。

6. 忘れがちな“送り火”の意味
送り火は「来た道を照らして安全に帰ってね」という愛情のサイン。炎の代わりにLEDランタンを置く家庭も増えていますが、火を扱うことで“命の温度”を感じる体験は貴重です。去年、小5の姪が「火ってあったかいけど切ないね」と呟いたのが印象的でした。消えゆく火に願いを重ねる——その瞬間、遠い昔から続くバトンを手渡された気がします。ここで送り火を絶やさないことが、供養のラストピースだと私は思うんです。

7. お彼岸とお盆、何が違う?
お彼岸は春分・秋分、「太陽が真西に沈む=極楽に続く直線が開く日」に行う仏教行事。対してお盆は夏、祖霊を招き送る年中行事へ変化したイベント。香りも違い、お彼岸はキクやリンドウ、お盆はミソハギが定番。お子様には「お彼岸は“通学路の横断歩道”で、ご先祖さまが渡って行く日。お盆は“おうちに泊まりに来る日”」と説明すると分かりやすいかもしれません。

8. まとめ
お盆は迎え火・供養・送り火──3つの灯りでご先祖さまと心をつなぐ時間です。
盆踊りは“供養のダンス”、経済効果は25億円、渋谷ではDJがお経をサンプリング。伝統はアップデートしながら未来へ続きます。
今年はぜひ一つでも新しい視点を試してみてください。「わが家流お盆」を作ることこそ、最良の供養になります。今日誰かに話したくなる豆知識
キュウリの馬とナスの牛、実は“軽い行きのタクシー・ゆっくり帰るリムジン”という説が主流。でも長野県の一部では逆に並べる地域もあり、「行きはのんびり景色を楽しんで、帰りは馬力全開で天へ戻る」そうです。トリビアですね!


 0120-136-841
0120-136-841