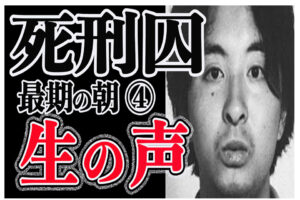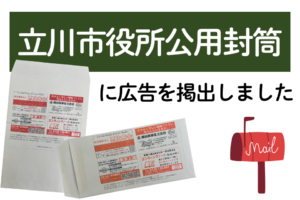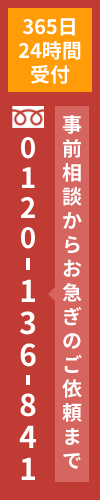「逆さ水って、水に熱湯を注いでぬるま湯をつくる儀式 ――なぜわざわざ手順を逆にするの?」。突然の別れが訪れた夜、親戚からそう頼まれて戸惑った経験はありませんか。実は日本には“逆さごと”と呼ばれる一連のしきたりがあり、故人をあの世へ導き、生者の世界と線を引くために生まれました。今日は逆さ水を入り口に、逆さ屏風・北枕・縦結びまで、その意味と由来を徹底解説。最後まで聞けば「なぜ?」が「なるほど!」に変わります。

目 次
1. 逆さ水―ぬるま湯づくりで示す境界
2.逆さ屏風・着物・草履のサイン
3.北枕と逆さ布団が示す“道標”
4.逆さ釘と逆さ文字で守る結界
5.夜間の葬儀と縦結びの意味
6.逆さごとは迷信?現代の視点
7.まとめ

1.逆さ水―ぬるま湯づくりで示す境界
桶(おけ)や洗面器にまず冷たい水を張り、あとから熱湯を注いで35〜40℃のぬるま湯を作る―これが正式な逆さ水(さかさみず)です。普段は「熱湯に水を足して冷ます」手順をあえて逆転させ、“生と死の境界”を浮き彫りにします。出来上がった湯は湯灌(ゆかん)で使い、左手で柄杓(ひしゃく)を持つ「逆さ手」で故人の足元から胸元へそっと掛(か)けるのが作法。
▷ 逆さ水のポイント
・水→熱湯という“逆転”が此岸(しがん)と彼岸(ひがん)を分けるサイン
・温度調整を家族が行うことで「最期のお世話をする」という実感が生まれる
・左手で柄杓を持つことで「日常の常識」をさらに崩し、非日常へ切替
実際、八王子市のA家では、孫が温度を確かめながら熱湯を足し、「おばあちゃん、気持ちいい?」と声を掛(か)けました。遺族にとっても、逆さ水は心の準備を整える大切な時間になるのです。

2.逆さ屏風・着物・草履のサイン
続いて“身の回り品を逆さにする”理由です。昔の農家では亡骸の後ろに逆さ屏風を立て、風を防ぎつつ「現世と逆転した空間」を示しました。また、納棺前に着物を左前にする“逆さ着物”、霊柩車へ向かう際に**逆さ草履(逆さ履き)**を履く習俗もあります。逆さ草履は右足に左用、左足に右用ををはかせたり、地域によっては底を上にして足裏に当てたることもあります。
▷ 逆さにする目的
・故人が「日常とは別世界にいる」と周囲へ知らせる
・魔除け:悪霊が混乱し近寄りにくい
・遺族の感情切替を助ける“儀式スイッチ”
たとえば府中市のB家では、祖父が剣道家だったため、竹刀袋を裏返して棺に添え「師範の世界を逆さに映す」演出を施しました。逆さは単なる形ではなく、“区別の印”として機能しているのです。

3.北枕と逆さ布団が示す“道標”
「北枕は縁起が悪い」は有名ですが、もとは釈迦入滅の方角が北だったという仏教由来です。さらに布団も頭と足を反対にして敷く逆さ布団にすることで、「ここは眠りではなく旅立ちの場」と示します。
▷ 北枕+逆さ布団の効果
・方位術で“北=冥界への道”を指し示す
・遺族が布団を触ることで、もう息をしていないという、死を現実として受容することになります。

4.逆さ釘と逆さ文字で守る結界
家屋そのものを“逆さ”で守る例が逆さ釘と**逆さ文字(逆書き)**です。棺を出す玄関の鴨居に釘を頭から打ち、魔が入るルートを攪乱。さらに門柱に「忌」の字を左右反転で書く地域もあります。釘は頭から打つことになるので、きりで下穴をあけて打つことになります。逆さ文字は左右反転の鏡文字にする場合と、南無阿弥陀佛を→佛陀弥阿無南ぶつだみあむな と並べることもあります。
▷ なぜ効く?
・上下左右を反転させ“こちらは異界”と示す
・視覚的に非日常を提示し、不浄の気を侵入させない
・共同体全体で死を共有し、弔意を表明
5.夜間の葬儀と縦結びの意味
かつて多摩の農村では、日中の作業を避け夜間の葬儀が一般的でした。暗闇は「生と死の境」であり、松明の光が魂を導くと信じられたからです。昭和20年ごろまでは、出棺は日没後18時から19時にはじめ、22時から23時ごろ墓地に到着し、翌早朝に火葬や土葬を行いました。多磨葬祭場が昭和6年に開設され、昭和30年代頃からは、式を朝6時頃から行い、7時30分ごろ出棺し火葬場に8時30分に到着し9時から火葬というようになったそうです。縦結びとは、通常は横向きに結ぶ蝶結びを、喪縄や供花の水引だけ縦一文字に結び「もう二度と解かない」意志を示します。
▷ 夜と縦結びの役割
・日常と時間帯を反転し“境界”を強調
・縦結びで「永遠の別れ」を直感的に伝える
・遺族が結び目を見て心を整える“スイッチ”

6.逆さごとは迷信?現代の視点
「全部昔の迷信でしょ?」という疑問も当然です。しかし心理学者の調査※では、逆さの儀式を体験した遺族の約78%が「区切りがついた」と回答。つまり“意味づけ”がグリーフケアを助けている側面があります。
▷ 現代葬儀での取り入れ方
・全部を再現するのではなく「象徴」を選ぶ
・逆さ水だけ行い、他は写真や動画で説明する方法も
・家族の宗旨と故人の希望を優先して取捨選択
実際、国立市のD家では逆さ水と縦結びを採用し、屏風はフォトスタンドで代用。「儀式がシンプルでも心は込められた」と語りました。逆さごとは、形より“思い”を届けるツールへ進化しているのです。
※日本グリーフケア学会 2023 年度調査

7.まとめ
逆さ水に始まり、屏風、北枕、釘、縦結び――“逆さごと”はすべて「日常を反転させ、死者と生者を正しく区切る」ための知恵でした。形を変えても、その核心は「迷わず送り、悔いなく見送る」こと。現代の私たちも、意味を理解し選択することで、大切な人を思う気持ちはより深く届きます。


 0120-136-841
0120-136-841