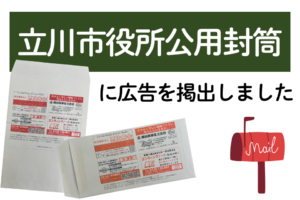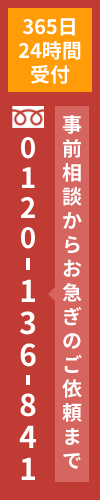拝島日吉神社の由緒
- 創建は室町時代(文明年間・1469〜1487)頃と伝えられます。
- 滋賀県坂本の日吉大社を勧請し、山王権現(日吉大神)を祀ったのが始まり。
- 古くから「拝島大師」の門前町とともに発展し、地域の鎮守として昭島・八王子方面の人々から信仰を集めました。

拝島日吉神社例大祭(榊祭)は、室町時代の創建由来をもとに江戸期から続く多摩を代表する秋祭り。
榊神輿の渡御と榊取り、人形山車や花棒振りといった勇壮かつ華麗な所作を特色とし、今日まで昭島の人々によって守り継がれています。今年は第258回目の例大祭です。

榊祭(例大祭)の起源
- 江戸時代中期にはすでに行われていたとされる古い祭礼。
- 特徴は「榊神輿」。榊を飾った神輿を深夜に渡御し、境内に戻す際に榊の枝を奪い合う「榊取り」が行われること。
- この榊は「家内安全・無病息災・五穀豊穣」の守りとして珍重されました。
- 江戸から多摩川を越えて参拝する人も多く、武州多摩地域を代表する夏祭りの一つとされました。

江戸時代〜明治期の変遷
- 江戸時代には「榊祭」「拝島の榊祭」と呼ばれ、川越の氷川祭や八王子まつりと並んで広域に知られる存在。
- 明治期には神仏分離に伴い、日吉神社として独立し、例大祭の形を整えました。
- 地域の町会が山車や神輿を奉納し、町ごとの人形山車や花棒振りが盛んに行われるようになりました。

現代の榊祭
- 毎年9月第2土・日を中心に斎行。
- 0時〜4時に榊神輿渡御、その後「榊取り」が行われるのが最大の見どころ。
- 午後には宮神輿渡御、人形山車、花棒振り、囃子連が加わり、町内を巡行。
- 榊を奪い合う勇壮さ、山車の華やかさ、花棒振りの躍動感で「多摩の三大祭礼」に数えられることもあります。

祭りの意義
- 榊=生命力と清浄の象徴。それを巡る行事を通じて、厄除けと五穀豊穣を祈願。
- また、町会ごとの山車・囃子・花棒が競演することで、地域コミュニティの結束を強める。
- 現代では文化財的価値も高く、地域の無形民俗文化財に位置づけられています。


 0120-136-841
0120-136-841