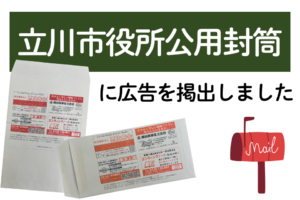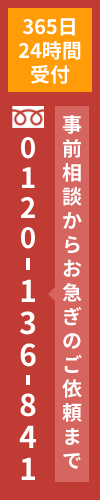うちは大丈夫――そう思っていませんか?深夜の病室で「費用はどなたが…」と看護師さんに聞かれ、言葉が出ない。現場で何度も見てきました。結論はシンプルです。「決めつけず、順番で考える」。まずは“使える原資”を確認し、次に“払う人”を話し合う。最後に“清算のルール”を紙に残す。地域や宗派、加入制度で違いがありますので、その都度そっとお伝えします。今日は、迷いをほどく実務の道筋を、やさしく一緒に整えていきましょう。

目 次
1.まず“自分” の原資を整える
2.“家族”が立て替えるときの流れ
3.“子供” に負担を残さない段取り
4.“長男が払う” 誤解と合意の作り方
5.“親”の立場で今できる備え
6.“自治体”と健康保険の給付
7.勤務先など“会社”由来の支え
1.まず“自分” の原資を整える
「自分のことは自分で」――その静かな決意が、ご家族を守ります。
Aさんは“エンディングノート”に生命保険の受取人、預金の所在、希望する規模を記載済み。家族会議は10分で完了しました。
要点は
▷ 生命保険(死亡保険金)は受取人へ直接支払われ、葬儀費の原資にしやすい
▷ 積立・互助会・葬儀社の事前見積で“規模と上限”を決める
▷ 預金は死亡後いったん凍結されることがあるため、少額の当座資金は別口座や現金も検討
―― 金額は地域・式場・時期で変わります。「どの程度の式にしたいか」を先に言葉にするのが安心の近道です。

2.“家族”が立て替えるときの流れ
突然の支払い。まずは見送りを整えたい。その気持ちを守るのが“清算の約束”です。
B家は長女がカードで一時決済。香典・保険金・遺産で後日清算し、兄弟で気持ちよく按分できました。
要点は
▷ 見積・請求・領収を一式保管しておくと後日清算がスムーズです
▷ 清算の順番の例として、香典→保険金→遺産について相続人で話し合いになります 保険金は受取額の割合をあらかじめ決めておくことができます。遺産の場合は割合を変えるには遺言書が必要になります。
▷ 相続放棄を検討中でも、社会通念上相当な葬儀費は“喪主立替→相続財産から清算”という考え方が一般的ではあります。
―― 支払い方法(分割・振込・後払い)は葬儀社で異なります。地域差もあるため個別に確認を。
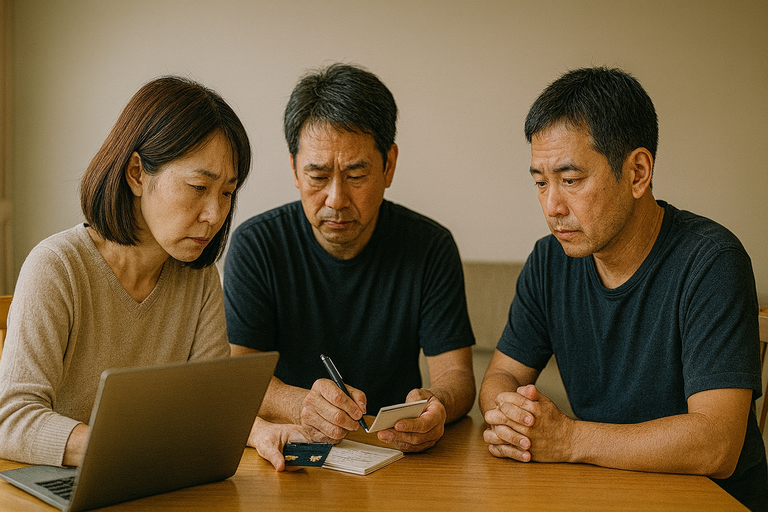
3.“子供” に負担を残さない段取り
子供に負担を残したくない 多くのご相談で最初に出る言葉です。
C家では、見積を子供たちとオンラインで共有。祭壇は控えめでも、お別れの時間を長く取り、費用と満足のバランスを家族で整えました。 要点は
▷ 事前相談で“必須・やめる・迷う”を三色分け、迷う項目はその時点で判断しましょう。
▷ 支払い役と窓口役を分けると負担が偏りにくい
▷ 保険・共済の受取人を最新に、連絡先をノートに明記
宗派・地域のしきたりは尊重しつつも、「子供の生活を守る」視点で選べば後悔が減ります。寺院対応は地域や宗派で異なるため、事前に確認をしましょう。

4.“長男が払う” 誤解と合意の作り方
「長男だから全部…」その一言に肩が重くなる方へ
D家では親戚の“昔の慣習”で緊張が走りましたが、「喪主=式の代表」「費用=家族で分担」を紙に残し、親戚にも共有。揉めずに済みました。
要点は
▷ 法律で“長男が必ず払う”とは定められていません
▷ 役割は「喪主=式の代表」「費用負担=家族で話し合い」が基本
▷ 香典の扱い(喪主個人か、全体の清算に回すか)を先に決める
地域の慣習・親族構成で異なります。「長男の責任」に偏らせず、断定より「合意の見える化」で安心を。

5.“親”の立場で今できる備え
「親として最後まで整えておきたい」。その優しさが、当日の心を支えます。
Eさんは“連絡リスト”“写真フォルダ”“希望する規模”をエンディングノートに記載していました。ご子息の皆さんは迷わず進行でき、無駄な追加も防げました。
· 要点は
▷ 規模と上限額を家族と共有し、小規模でも“別れの時間”は確保できます
▷ 葬儀社の会員・互助会・保険・共済の確認、預金の所在メモをエンディングノートへ
▷ 死後事務(遺品・公共料金)も簡単にリスト化、スマホのロック解除はわかりやすくしとくと安心です
無理に高額な契約は不要です。“想い”と“予算”をセットで残す。これがご子息への負担を軽くします。

6.“自治体”と健康保険の給付
制度は難しく見えても、使える支えは身近にあります。
名称や金額は違っても、多くの方に該当する仕組みがあります。
Fさんは国民健康保険の「葬祭費」を申請。必要書類をそろえ、後日支給で家計が助かりました。
要点は
▷ 国保の「葬祭費」、協会けんぽ・健保組合の「埋葬料/埋葬費」等があり、支給要件・金額・申請期限は加入先や自治体で異なります(各窓口で確認を)
▷ 「火葬許可証=火葬に必要な役所の許可書類」。申請やコピー提出を求められる場合あり
▷ 生活保護の「葬祭扶助」は要件や範囲に厳格な基準があります(福祉事務所で個別相談)
火葬場や式場の料金も地域差が大きい項目です。迷ったら“総額の上限→内容調整”の順で考えると失敗が減ります。請求期限は葬儀をした日から2年以内とか決まっていますので早めに手続きをしてください。

7.勤務先など“会社”由来の支え
「会社から何か出るのかな?」――見落としがちな安心材料です。
Gさんは勤務先の慶弔規程で弔慰金・特別休暇・共済からの
給付があり、立替負担が軽くなりました。
要点は
▷ 会社の慶弔規程・共済・労災(業務上死亡の場合)の確認
▷ 労働組合・団体保険の弔慰金、退職金規程の死亡取扱いなども要チェック
▷ 故人が会社役員・自営業のときは、会計・税務の扱いが関わることがあります税理士にチェックしましょう。
葬儀社の分割・カード・後払いの可否も各社で異なります。無理のない支払い計画を一緒に選びましょう。
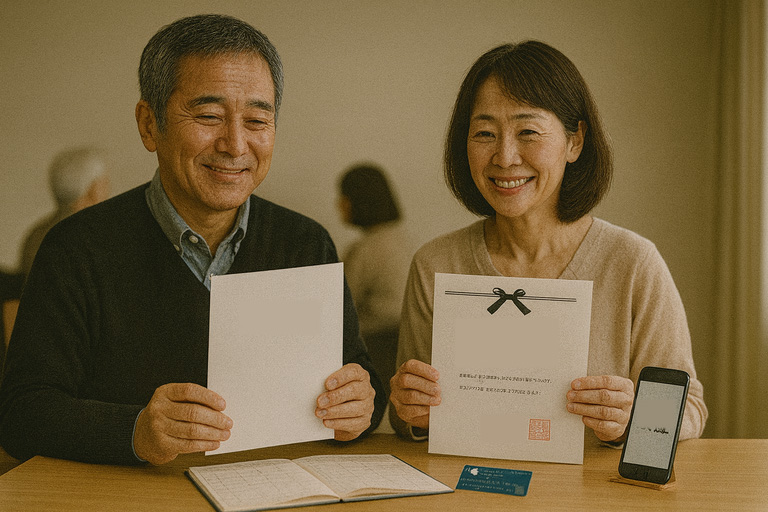
8.まとめ
葬儀費用の“誰が払うか” 答えは「決めつけず、順番で整える」です。〈自分〉の原資と上限を言葉にし、〈家族〉で清算の約束を先に。〈子供〉の生活を守る段取りを作り、〈長男〉に偏らない合意を書面化。〈親〉として想い+予算をセットで残す。〈自治体〉や健康保険の給付を確認し、〈会社〉の支えも活用――この流れなら、迷っても戻れます。地域・宗派・加入制度で違いがありますので、詳細は各窓口や葬儀社に遠慮なくお尋ねください。事前相談は、心の余白をつくる準備です。


 0120-136-841
0120-136-841