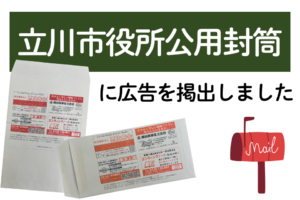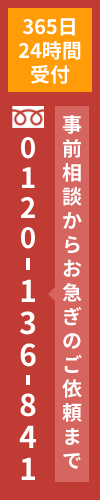うちはまだ大丈夫。そう思っていても、命日が近づくと「何から手を付ければ…」と不安になりますよね。大丈夫、一緒にやさしく整理していきましょう。今日のテーマは「一周忌までにやること」。法要の準備や進行、マナー・装い・表書き、案内・文面、お墓・納骨・仏壇、相続・公的手続き、そして暮らし・心のケア、年中行事・喪中関連、宗派別ポイントまでを、7項目で道筋にします。地域や寺院、宗派によって作法や相場は変わりますので、「目安」としてお聴きくださいね。

目 次
1.法要準備・進行の全体像(7項目の地図)
2.マナー・装い・表書きの整え方
3.案内・文面は“迷わせない”が正解
4.お墓・納骨・仏壇まわりのポイント
5.相続・公的手続きは期限を“言葉”で把握
6.暮らし・心のケアと記録の残し方
7.年中行事・喪中関連と宗派別ポイント
8.まとめ

1.法要準備・進行の全体像(7項目の地図)
- 一周忌の「法要、準備、進行」。言葉は聞くけれど、具体的な段取りが見えない…そんな戸惑いは自然なことです。
- 実例:あるご家族は、命日が平日だったため僧侶・親族の都合を優先して土日に前倒し。進行表を作ったことで、当日は落ち着いて参列できました。
- 要点整理
▷ 7項目の地図… - ①日程調整は命日の前倒し・土日に選定します。
- ②会場選びは寺院や自宅・会館・墓前です。森の風ホールでも毎月法要で利用される方は多くいらっしゃいます。
- ③僧侶依頼とお布施の目安。
- ④施主の役割と進行表。
- ⑤出欠管理と座席決め。
- ⑥会食の段取り。
- ⑦引き出物(粗供養)の用意。
「御車代=移動費のお礼」「御膳料=会食に代わるお食事代のお礼」のことです - 進行例…開式→読経→焼香→法話→回向(故人・先祖に功徳をささげること)→墓前回向→会食。相場や作法は地域差・寺院差があります。

2.マナー・装い・表書きの整え方
- 服装や香典、表書き。「間違えたら失礼かな…」という不安は誰にでもあります。
- 実例:喪服で統一し、数珠・袱紗・ハンカチを小さなポーチに。受付もスムーズになります。
- 要点整理
▷ 服装…喪服/準喪服。季節に応じてコートは会場前で脱ぐ。靴やバッグは控えめに。
▷ 香典…「御仏前」「御霊前」の使い分けは宗派で異なります。表書き・蓮のしは地域で違いあり。
▷ 供花・供物・線香…事前に施主へ確認。花札や立札の表記も会場ルールに合わせる。
▷ 挨拶文例(施主)…「本日はお忙しい中お集まりいただき…」と短く感謝を。長文より“温度”です。
※ 作法・相場は寺院・地域で異なるため、事前に確認すると安心です。

3.案内・文面は“迷わせない”が正解
- 案内状が遅れたり情報が抜けると、当日あわててしまいます。
- 実例:返信フォーム(QR)と紙の返信ハガキを併用。地図画像・駐車場・会食有無を明記します、欠席者には後日礼状を郵送します。電話での確認も大切です。
- 要点整理
▷ 案内・文面には…日時/会場/読経開始時刻/会食の有無/服装目安/香典辞退の有無の記載を確認します。
▷ テンプレ…「案内状」「礼状」「御礼状」を用意し、メール・郵送どちらにも対応。
▷ アクセス…地図、公共交通、送迎の有無、 。
欠席の方には後日のご挨拶を。気持ちが伝われば十分です。

4.お墓・納骨・仏壇まわりのポイント
- 納骨や位牌、本位牌の手配はタイミングが難しいですよね。
- 実例:四十九日で納骨できなかったご家庭が、一周忌に合わせて墓石の追加刻字と納骨堂の手続きを同時進行。負担が分散できました。
- 要点整理
▷ 納骨…時期は四十九日・百か日・一周忌などが目安です。無理のない日程で行いましょう。
▷ 墓石の追加刻字…戒名(法名)・没年月日を確認。彫刻は納期に余裕を持って行います。
▷ 位牌・仏壇…本位牌の開眼(入魂)、過去帳の記載。
▷ 形が決まらないときは…納骨堂・永代供養・手元供養という選択肢も。
※ 墓前供養や作法は宗派・霊園規定により異なります。

5.相続・公的手続きは期限を“言葉”で把握
- 書類や期限が多くて、心が追いつかない。そんな時こそ、用語で覚えるとラクです。
- 実例:家族会議で「期限もの」を一覧化。税理士・司法書士・年金窓口の順で相談し、落ち着いて進められました。
- 要点整理
▷ 準確定申告=4か月/相続放棄・限定承認=3か月/相続税申告=10か月(いずれも一般的な目安です)。
▷ 遺産分割協議書・相続登記(不動産)・名義変更(銀行・車・携帯・公共料金)。
▷ 年金・健康保険…遺族年金、葬祭費・埋葬料の申請には時効があります。
▷ 生命保険…保険証券・保険会社へ請求します。
▷ デジタル遺品…ID・パスワードの整理、契約解約、追悼設定。追悼設定とはアカウントを守りながら想い出を残す“デジタル供養の準備”です
※ 具体の要件・期限は自治体や管轄窓口で必ずご確認ください。

6.暮らし・心のケアと記録の残し方
- 「片付け」は心の整理とつながっています。急がなくて大丈夫です。
- 実例:形見分けの“ルール”を家族で合意し、遺品整理は専門業者に見積を取り比較。写真・動画で法要の記録を残し、アルバムに。
- 要点整理
▷ 形見分け・遺品整理…トラブル回避のため“合意メモ”を残しましょう。
▷ グリーフケア…つらい時は一人で抱えず、家族会議や専門窓口へ。
▷ 家計見直し…葬儀費用の精算、香典返しの最終確認。
▷ 記録…法要の写真・動画は参列できなかった方への共有にも。そっと、さりげなく。

7.年中行事・喪中関連と宗派別ポイント
- お盆や彼岸、喪中はがき…“いつ・何を”が曖昧になりがち。
- 実例:初盆(新盆)や春秋彼岸(しゅんじゅうヒガン)に合わせてお墓参りを計画。喪中はがきは秋以降に投函し、年明けには寒中見舞いでご挨拶。
- 要点整理
▷ 年中行事…初盆/新盆、春彼岸・秋彼岸は無理のない範囲で供養を。
▷ 喪中関連…喪中はがきの時期、喪中明けの寒中見舞い文例。
▷ 宗派別ポイント…焼香回数や合掌の作法、法話の位置づけは浄土真宗・曹洞宗・真言宗・日蓮宗・臨済宗などで違います。
▷ 表書き…「御霊前」「御仏前」の使い分けは基本的には四十九日を過ぎていれば御仏前を使いましょう - ※ すべて“地域差・寺院差あり”を前提に、迷ったら施主・寺院へ一言相談を。

8.まとめ
一周忌は、故人を想いながら暮らしを整える大切な節目でしたね。今日は「法要準備・進行」「マナー・装い・表書き」「案内・文面」「お墓・納骨・仏壇」「相続・公的手続き」「暮らし・心のケア」「年中行事・喪中関連と宗派別ポイント」を“7項目”として見取り図にしました。すべてを完璧にしなくて大丈夫。地域や宗派で答えは少しずつ違います。分からない所は、寺院・自治体・専門家、そして私たちに気軽にご相談ください。無理のないペースで、一歩ずつ。


 0120-136-841
0120-136-841