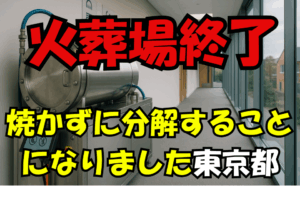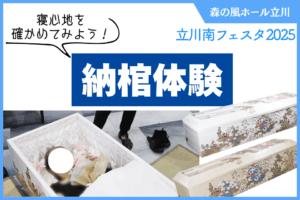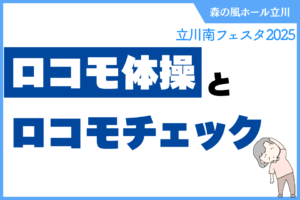突然ですが、あなたはこんな疑問を持ったことありませんか?
「もし自分が亡くなったら、遺産はちゃんと希望通りに分配されるの?」
あるいは、家族や大切な人が遺言を残していなかったら、何が起きるのか……想像するとちょっと怖いですよね。でも安心してください!この動画では、公正証書遺言がどんなものか、そして死亡後に具体的に何が起きるのかを分かりやすく解説していきます。

目 次
- 公正証書遺言とは?
- 公正証書遺言の費用について
- 行政書士のサポートを受けるべきか
- 公正証書遺言が発動する流れ
- まとめ
1.公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人という専門家が関与して作成される遺言書です。これがあることで、遺言内容が法的に確実に効力を持ちます。具体的には次のような特徴があります:
- 信頼性が高い:専門の公証人が法律に基づいて作成するため、不備がありません。
- 改ざんや紛失のリスクがない:公証役場で保管されるため、安全性が高い。
- 家族間のトラブルを防ぐ:明確な証拠として認められるため、相続人間での争いを防ぐことができます。
ここで、一つ具体例を挙げてみましょう。
例えば、Aさんが公正証書遺言を作成して「自宅は長男に、預金は次男に」と指定していた場合、Aさんの死後にその遺産分割の内容が明確になります。これがなければ、相続人たちは遺産分割協議を行わなければならず、意見が対立する可能性もあります。
また、公正証書遺言は、認知症や病気などで判断能力が低下する前に作成しておくことが重要です。判断能力が低下した後では遺言を作成することが難しくなるため、早めの準備が大切です。

2.公正証書遺言の費用について
公正証書遺言の作成費用は、遺言に記載する財産の額によって異なります。具体的には、以下のような料金体系になっています。
- . 公証役場の手数料
公証人の手数料は、遺言書に記載される財産の総額に基づいて決まります。
- 財産額が 100万円以下 の場合:5,000円
- 財産額が 100万円超~500万円以下 の場合:11,000円
- 財産額が 500万円超~1,000万円以下 の場合:17,000円
- 財産額が 1,000万円超~3,000万円以下 の場合:23,000円
- 財産額が 3,000万円超~5,000万円以下 の場合:29,000円
- 財産額が 5,000万円超~1億円以下 の場合:43,000円
- 財産額が 1億円超~3億円以下 の場合:43,000円+5,000円×(1億円超過額/1,000万円)
財産額が大きくなるほど手数料も上がります。
- 遺言の加算料金
遺言に特定の条項を追加したり、遺言執行者を指定する場合には、追加料金が発生することがあります。
- 遺言執行者の指定:11,000円
- 特別な内容の記載(複雑な分割や条件付きの相続など):手数料が加算される可能性あり
- 証人報酬
公正証書遺言を作成する際には、法律により2名の証人が必要です。通常、証人を公証役場が手配する場合、その報酬として1人につき 5,000円~10,000円 の費用がかかります。
- 必要書類の取得費用
遺言書を作成する際に必要な書類(戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書など)を準備するための費用も別途必要です。
- 戸籍謄本:450円/1通
- 登記簿謄本:600円~
- 固定資産評価証明書:300円~数千円(地域による)
合計の目安
例えば、財産額が 1,000万円 の場合の費用は以下のようになります:
- 公証人手数料:17,000円
- 証人報酬:10,000円(2名分)
- 必要書類の取得費用:約5,000円
合計:約32,000円~
公正証書遺言の費用は「遺産のトラブルを防ぐ」ための安心料と考えると、高いとは言えないかもしれません。また、正確な費用を把握したい場合は、公証役場に直接相談することをおすすめします。

3.行政書士のサポートを受けるべきか
公正証書遺言を作成する際、自分一人で進めるべきか、それとも行政書士のサポートを受けるべきかについてお話しします。
公正証書遺言は自分で公証役場に申し込むことも可能ですが、行政書士や専門家と一緒に進めるのもおすすめです:
- 専門的なアドバイスが受けられる 財産の分配方法や法律的な問題について、行政書士は専門知識を持っています。適切なアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
- 手続きがスムーズ 必要書類の準備や公証人とのやり取りなど、手間のかかる手続きを行政書士が代行してくれるため、スムーズに進行します。
- 複雑な事情に対応 再婚家庭や相続人が複数いる場合、遺産分割に関する事情が複雑になることがあります。こうした場合でも、行政書士が適切に対応してくれます。
行政書士に依頼する場合の費用は、10万円前後が相場ですが、公正証書遺言の信頼性や手続きの安心感を考えれば十分に価値があると言えます。

4.公正証書遺言が発動する流れ
発動する流れを見ていきましょう。
- 死亡届の提出 遺言者が亡くなると、まず家族が市区町村役場に死亡届を提出します。
- 遺言書の確認 公証役場に問い合わせ、公正証書遺言が存在するかを確認します。公証役場は遺言書を厳重に管理しているため、確認は迅速に行われます。
- 遺言内容の開示 公証人が遺言書を開示し、その内容を相続人たちに通知します。この段階で内容が法的に有効であることが確認されます。
- 相続手続きの開始 遺言に基づいて、相続財産の分配が進められます。たとえば、不動産の名義変更や預金の引き出しなどが具体的に行われます。
このプロセスの中で重要なのは、遺言が公正証書であることによって、遺産分割協議が不要になる点です。これは家族間の争いを防ぎ、迅速な相続手続きを可能にします。

5.まとめ
公正証書遺言は、家族や大切な人たちに安心を与えるための素晴らしい手段です。特に、財産を持つ人や複雑な家庭事情がある場合には、ぜひ作成を検討してください。
また、公正証書遺言の作成に関する具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。


 0120-136-841
0120-136-841