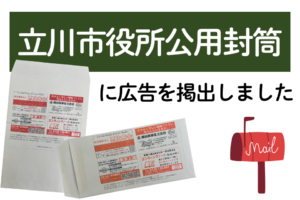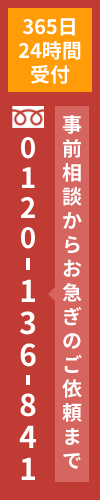故人やそのご遺族が生活保護を受給されている場合、ご葬儀についてさまざまな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、生活保護受給者の方のご葬儀に関する「葬祭扶助制度」について、申請の流れや必要な手続き、費用面での支援内容などをわかりやすくご説明いたします。
本記事を通じて、大切な方との最期のお別れに向けた準備のお手伝いができれば幸いです。
生活保護受給者でも必要最低限のお葬式をあげられます
大切な方が生活保護を受給されていた場合でも、最低限のご葬儀を執り行うことが可能です。「葬祭扶助制度」を利用することで、「火葬してご遺骨を納める」ための最低限の費用のご支援を受けられます。
支給される費用は自治体によって異なりますが、一般的には以下の費用が含まれます。
- 死亡診断書等の作成費用
- 火葬費用
- 棺や骨壺の費用
- ドライアイス代
- 安置施設使用料
- 霊柩車の費用
- 病院からの移送費用
など
お住まいの自治体によって「生活保護葬」「福祉葬」「民生葬」と名称は異なりますが、ご葬儀の内容はほぼ同様です。
この制度では、検案、ご遺体の搬送、ご安置、火葬といった最低限の葬儀ができる費用が給付されます。大切な方の尊厳を保ち、最期のお別れを大切にされたい方に、安心してご利用いただける制度となっております。
葬祭扶助制度を利用する条件
葬祭扶助制度は、以下のいずれかに当てはまる場合に利用することができます。
・故人または喪主(ご遺族)が生活保護を受けるなど困窮している
ただし、故人様やご親族様に十分な資産がある場合は、葬祭扶助制度をご利用いただくことができません。これは、本制度が経済的にお困りの方への支援を目的としているためです。
具体的には、故人様の預貯金や保険金、ご親族様の資産などで葬儀費用を賄える場合は対象外となります。また、福祉事務所のケースワーカーによる判断で、生活状況が支給基準に該当しないと判断された場合もご利用いただけません。
・故人に扶養義務者がおらず、ご遺族以外の第三者が葬儀を手配する
故人様に扶養義務者がおらず、家主や民生委員が葬儀を行う場合は葬祭扶助を受けることができます。
葬祭扶助制度のご利用をお考えの方は、事前に福祉事務所にてご相談いただき、支給条件をご確認くださいますようお願いいたします。
費用負担ゼロですが葬儀の形式は限定されます
葬祭扶助制度を利用することで、ご自身の費用負担なくご葬儀を執り行うことが可能です。葬祭扶助の範囲内であれば、葬儀に必要な基本的な費用が給付されるため、施主様の費用負担は発生いたしません。
ただし、葬祭扶助制度を利用してご葬儀を執り行う場合、その形式は「直葬」(火葬式)に限定されます。これは、国からの給付金が必要最小限の費用に対応する制度であるためです。
直葬では、お通夜や告別式は行わず、ご遺体を火葬場へ搬送後、すぐに火葬を執り行います。火葬後は拾骨し、骨壷に納めて終了となります。
なお、僧侶による読経や戒名授与、精進落とし(ご遺族やご親戚を中心にした会食)などは制度の対象外です。
また、この制度を利用せずにご葬儀を執り行う場合は、すべての費用を自己負担することになりますので、葬祭扶助制度の条件に当てはまる方は、申請の手続きを忘れないようにしましょう。

葬祭扶助制度の上限金額
生活保護受給者の方がご葬儀を執り行う際の葬祭扶助制度には、給付金の上限額が設けられております。国が定める基準では、成人の方は21万5,000円、12歳未満のお子様の場合は17万2,000円が上限です。ただし、自治体によって給付金の上限額が異なる場合もございます。
そのため、葬祭扶助制度のご利用をお考えの方は、事前にお住まいの自治体窓口にて、具体的な給付条件をご確認いただくことをおすすめいたします。
生活保護受給者のお葬式の流れ
生活保護受給者が、葬祭扶助制度を利用した場合のお葬式の流れは下記のように進みます。
- 福祉事務所へ連絡
- 葬祭扶助の申請・審査
- 葬儀社への依頼
- お葬式
- お支払い
以下でそれぞれの具体的な内容についてお伝えします。
1.福祉事務所へ連絡
生活保護受給者の方のご葬儀を執り行う際は、まず申請者の住民票がある福祉事務所への連絡が必要となります。葬祭扶助の申請は必ずご葬儀の前に行う必要があるため、お早めのご対応をお願いいたします。
申請には、死亡診断書などの故人様の死亡を証明する書類と葬祭扶助申請書が必要です。申請書の様式は自治体によって異なりますので、窓口でお受け取りいただくか、自治体のホームページからご確認ください。
2.葬祭扶助の申請・審査
葬祭扶助制度のご利用には、申請者の居住地域の福祉事務所で申請・審査が必要となります。申請後、調査が行われ、制度利用の可否が判断されます。
調査では、故人様の預貯金の有無や、ご遺族様の経済状況などが確認されます。その結果、経済的な困窮が認められた場合に制度の利用が許可されます。ただし、故人様に十分な資産があった場合や、ご遺族様に葬儀費用を負担する余裕があると判断された場合は対象外となります。
このように、生活保護を受給されている方でも、状況によって制度をご利用いただけない場合がございます。
3.葬儀社への依頼
葬祭扶助制度の申請が通りましたら、葬儀社へのご依頼を進めます。この際、必ず葬祭扶助制度を利用する旨を“事前”にお伝えください。
制度をご利用の場合、直葬に対応している葬儀社をお選びいただく必要がございます。

4.お葬式
葬祭扶助制度をご利用いただく場合のご葬儀は、直葬の形式で執り行われます。これは、お通夜や告別式を行わず、ご火葬を中心とした簡潔な形式の葬儀になります。
ご参列者様には、直葬でのご葬儀となる旨を事前にお伝えいただきますよう、お願い申し上げます。
5.葬儀費用のお支払い
葬祭扶助制度をご利用いただく場合、費用のお支払いは福祉事務所から葬儀社へ直接行われます。そのため、喪主様や施主様がお支払いについてお手続きいただくことは基本的にございません。
具体的には、葬儀社から福祉事務所へ費用が請求され、福祉事務所から葬儀社へ直接支払われる仕組みとなっております。申請手続きが適切に完了していれば、ご遺族様の実質的なご負担はありません。
葬祭扶助の申請が遅れた場合は?
葬祭扶助制度のご利用には、必ずご葬儀の前に申請を行っていただく必要がございます。
例えば、ご葬儀の費用をご自身で立て替えてお支払いされた後に申請をされましても、お支払いができる資産をお持ちだったとみなされ、制度をご利用いただくことができません。
そのため、お急ぎの場合でも、必ず事前に福祉事務所への申請をお済ませください。
香典を受け取っても問題ない?
葬祭扶助制度をご利用される場合でも、ご参列者様からの香典はお受け取りいただくことができます。これは、香典が収入としてみなされず、制度利用の可否に影響を与えないためです。
お受け取りになった香典は、故人様のお墓や納骨の費用など、ご遺族様のご判断でご自由にお使いいただけます。また、香典は申告の必要もなく、葬儀費用として徴収されることもございません。
ただし、香典返しの費用は葬祭扶助の対象外となりますので、その点はご留意ください。
生活保護受給者のお葬式まとめ
この記事では、生活保護受給者の方のご葬儀について、葬祭扶助制度を中心に解説してまいりました。葬祭扶助制度は、経済的にお困りの方でも、大切な方との最期のお別れを尊厳を持って執り行えるよう設けられた制度です。
葬儀は直葬形式で執り行う、給付金の上限額がある等、いくつかの制限はございますが、基本的な葬儀費用の負担なくご葬儀を執り行うことが可能です。ただし、制度のご利用には事前の申請が必要不可欠です。また、故人様やご遺族様の経済状況によって利用可否が判断されるため、お早めに福祉事務所やケースワーカーにご相談ください。
もしご不明な点がありましたら、弊社のスタッフがサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 0120-136-841
0120-136-841