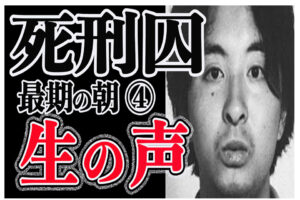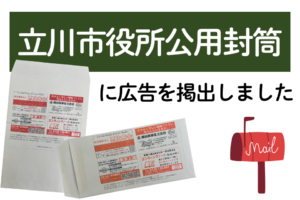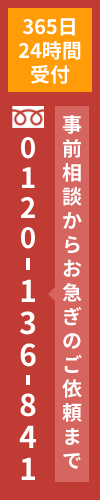家族が 亡くなった ―― 悲しみに浸る時間さえ…与えられず・・・でも、本当に大変なのは、ここからなんです。
亡くなった翌日の2日目から14日目にかけて、やるべきことが一気に押し寄せてきます。火葬 年金の停止など 次々と迫る“手続きの嵐”。しかも、これらの多くには、期限があり 過ぎれば、保険金が受け取れない…思わぬ支払い命令の“課徴金”となるリスクまであるんです。
だからこそ、今、この記事でお伝えします。大切な人を見送った そのあと、残されたアナタが、やるべきこと…どこで、何が必要で?いつまでに?・・・を具体的に、わかりやすくお伝えします。
この記事は、未来のアナタを守る準備でもあります。

亡くなって2日目〜7日以内までに やるべきこと
①死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
亡くなった その日(1日目)に 医師から「死亡診断書」や「死体検案書」を渡されます。医師が死亡を確認したことを証明する書類です。
そしてこの死亡診断書は、亡くなった日を含めて7日以内に、役所へ提出しなければいけません。
7日以内に行わないと 法律違反をしたことになり、法律違反の罰則として過料を支払うことになります。具体的には、以下の3つの書類をセットで提出します。
・死亡診断書(または死体検案書)
・死亡届(役所の戸籍課で記入)
・火葬許可申請書(役所の戸籍課で記入 一部自治体では不要)
これらを「戸籍課」で 提出します。死亡届は、戸籍に「亡くなりました」という記録を正式に登録するためのもの。火葬許可申請書は、火葬を許可してもらうためのものです。
ここまでの手続きは 弊社では無料で代行しております。時々、「私たちでやります」と おっしゃる方がいらっしゃいます。でも是非、頼ってください。むしろ、お任せくださいと 私は 思います。
なぜならば、ご遺族は 深い悲しみの中で、病院での退院手続き・親戚や関係者への訃報連絡など、すべて ご遺族で担うのは ほぼ不可能だと思うからです。
葬儀社は役所の手続きにも 慣れており、7日以内という日数の制限や 火葬場予約にも的確に対応し、ご遺族の負担を減らします。
大切な方を見送るために、心の準備に集中できる時間をつくることが、残された ご遺族にとって 本当に必要な“最初の支え”だと、私は思っております。弊社は無料です。役所手続きは お任せください。

亡くなって 2日目〜14日以内までに やること
①ご葬儀――
それは、人生で最も深い“大切な人との お別れ”の時間です。亡くなって2日目から14日目くらいまでの間に、通夜、告別式、葬儀、火葬、そして収骨が行われるのが一般的です。冬の時期、とくに東京では火葬場の予約が取りづらく 多くの場合、亡くなってから14日までには 火葬を行っております。

式場の手配、宗教者の依頼、参列者への案内、料理や返礼品の選定など――決めることが本当に多く 心身ともに本当に 大変です。これらはすべて、葬儀社と一緒に、1つ1つ 進めていくことができます。そして、火葬日に 絶対に忘れてはいけないのが…
1、で交付された「火葬許可証」です。
この証明書がないと、火葬できません。これは火葬当日、火葬場の管理事務所に提出し、火葬が可能になる重要な書類です。紛失してしまうと、その日に火葬が出来亡くなり、再発行が必要になります。弊社では、火葬許可証は責任をもってお預かりし、火葬場まで安全にお持ちいたしますので、ご安心ください。
火葬が終わると、提出していた火葬許可証が「火葬執行済」の印を押されて返されます。この書類は、そのまま「埋葬許可証」として扱われ、後日、お墓や納骨堂に納骨する際に必要になります。

この「埋葬許可証」も 無くさないよう、大切に保管しておきましょう。
②葬儀代の清算
請求書を受け取ったら、葬儀を行った日から約2週間以内に清算しましょう。この領収書は、葬祭費支給の申請に必要です。捨てずに大切に保管しましょう。
この葬祭費とは国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなった際、加入先の自治体から「葬祭費」が給付されます。必要なものは葬儀費用の領収証で、給付金額は自治体によって異なり 約3万円〜7万円です。申請期限は葬儀をとり行った日の翌日から2年以内です。自治体によっては直葬は給付が無いところもあります。確認しましょう。
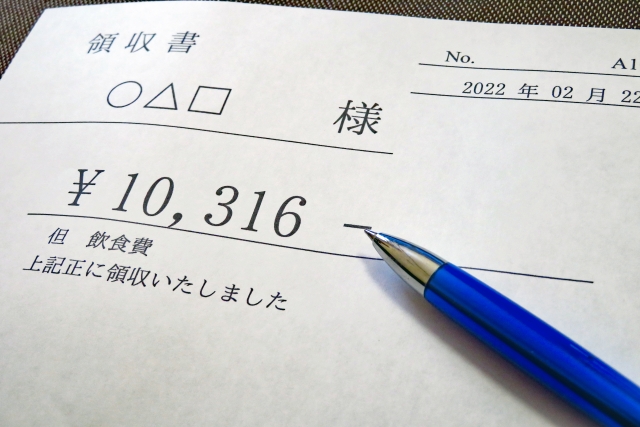
③除籍謄本・住民票の除票の取得
■ 除籍謄本とは?故人が戸籍から外れたこと・亡くなったことを証明する書類で、相続・保険金・不動産の名義変更などに必要です。
申請人は、配偶者・子・親・兄弟姉妹などの直系親族、または委任された代理人。故人の本籍地がある市区町村役所(戸籍課)で取得します。
【遠方の場合】は 郵送請求が可能です。
■ 住民票の除票
故人の生前の住民登録が削除されたことを証明する書類で、年金や保険、銀行手続きなどでよく求められます。
申請人は、故人と同じ世帯だった人、法定相続人、または委任された代理人。
故人の住所地の市区町村役所(市民課)の窓口または郵送で行い、自治体によってはオンライン申請も可能。
申請する方の 本人確認書類(運転免許証など)、故人との関係がわかる戸籍(必要に応じて)が必要です。
*両方とも亡くなって10日目くらいまでに 取得しておくのが おすすめです。
④年金の停止手続き
受け取っていた年金の種類により、手続き先が異なります。
厚生年金の場合➡️年金事務所で、亡くなってから10日以内に
国民年金の場合➡️亡くなってから14日以内に、市区町村役場の年金担当窓口で行います。

必要なものは、死亡診断書または死亡届の写し・年金証書(年金手帳)
紛失していても大丈夫、番号がわかればOK。亡くなった方の戸籍謄本、または除籍謄本。役所の戸籍課で取得。申請者(遺族)の 本人確認書類です。
⑤健康保険などの資格喪失手続き
🔳国民健康保険の資格喪失届➡️国民健康保険に加入していた方。期限は 亡くなった日から14日以内、提出先は 故人が住んでいた市区町村の役所(保険年金課など)です。
持ち物は、死亡を証明する書類(死亡診断書の写しなど)・健康保険証・手続きする人の本人確認書類(免許証など)
🔳会社の健康保険に加入していた場合➡️手続き期限は、原則5日以内。厳密な期限は健保ごとに異なるが 早めが望ましい。勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに提出します。
*手続きは 会社の人事・総務担当者が代行します。
🔳後期高齢者医療保険の資格喪失届➡️後期高齢者医療制度に加入していた方
期限は、亡くなった日から14日以内。 提出先は 故人が住んでいた市区町村の国保年金課などです。
持ち物は、後期高齢者医療被保険者証・死亡診断書の写し、または 除籍謄本。
遺族の本人確認書類です。
🔳介護保険の資格喪失届➡️介護保険の要支援・要介護認定を受けていた方
期限は、亡くなった日から14日以内提出先は 市区町村の「介護保険担当課」「福祉課」など
持ち物は、介護保険被保険者証・死亡診断書の写し・手続きする方の身分証明書
これら申請者は、故人と同一世帯の遺族、配偶者・子や 故人の法定相続人(別居していてもOK)です。
この記事のまとめ
親が家族が 亡くなったあの日、悲しむ時間すらないまま、現実が押し寄せてきた。亡くなってから 14日目までは、葬儀・年金や保険の停止・名義変更・届け出など、 “やらなければならないこと”が、次々とやってきます。
どれも期限を過ぎれば「損」や「トラブル」につながるものばかり。
でも、これらは単なる“事務作業”ではありません。故人の人生を、きちんと“締めくくる”大切な節目です。しんどいのは、よーくわかります。
手続きが不安なとき、どうしていいか迷ったとき、お葬式が終わったあとでも、私たちにご相談ください。地域密着の葬儀社として、無料でアドバイスやご提案をさせていただいております。
そのすべてを、遺族のあなただけで背負い込まないでください。そして、ひとつひとつの手続きを進めていくたびに、「ちゃんと送れたんだ」と、ご自身の心が少しずつ追いついてきます。
それは、亡き人への“けじめ”であり、あなた自身の“再出発”でもあります。
この記事が、アナタを支える その第一歩になれば幸いです。

 0120-136-841
0120-136-841