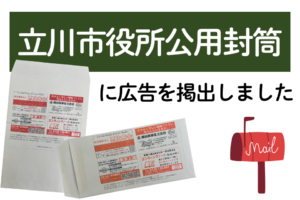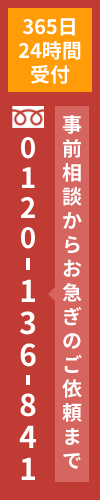皆さん、ご存じですか?大切なご家族が 亡くなった、その瞬間。深い悲しみで胸がいっぱいになりながらも、葬儀の準備をしなければなりません。そんな時にですが 実は「亡くなったら、もらえるお金」というのがあるんです。
でも…ここが大事です
そのお金は、ただ黙っていても 死亡届を出しても、自動的には 入ってきません。必ず各々 “申請”が必要で、しかも 期限つきなんです。
「悲しいから、今はとても手続きなんて…」と 後回しにされる方、非常に 多いです。でも、手続きをしなければ、受け取れるはずだった数十万、時には100万円以上のお金が、なかったことになってしまうんです。
「もっと早く知っていれば」と、悔しい思いをされるご遺族を 何度も見てきました。だからこそ、今日の動画は永久保存版です。
「亡くなったらもらえるお金」は実はいくつも種類があり、1つだけ取り上げて説明しているYouTubeは多くありますが、網羅しているものは ほとんど無く、この記事だけです。知っているかどうかで、葬儀の負担も、その後の暮らしの安心も、大きく変わるのです。 ご葬儀関連は 知ることからスタートします。

埋葬料・埋葬費・・葬儀・埋葬にかかるお金
葬儀・埋葬にかかるお金として「埋葬料・埋葬費」
期限:死亡日から2年以内
必要な書類:
①故人が亡くなったことを確認できる書類 次のいずれか 1点が必要
①死亡診断書・死体検案書の写し
埋葬許可証または火葬許可証の写し
戸籍(除籍)謄本・抄本、住民票の写しなどのうち、どれか1つ
③ 葬儀社の領収書原本
④申請者の印鑑・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・それと 振込先の口座情報(通帳、キャッシュカードなど)
申請者:喪主や葬儀を行った遺族
申請場所:勤務先の健康保険組合、または 市区町村の国保窓口です
支払い金額: 会社員なら健康保険から5万円、国保加入者なら自治体から5万円程度支給されます

年金関連:未支給年金・死亡一時金・遺族年金・寡婦年金
ここは金額も大きく、見落としやすいポイントです。
期限: 死亡から5年以内
必要な書類:
亡くなった方の・年金証書・死亡診断書・戸籍謄本・年金証書・死亡診断書・戸籍謄本
請求者の ・印鑑請・通帳・マイナバー・本人確認書類
請求者:配偶者や生計を一にしていた親族
申請場所: 年金事務所
期限:死亡日の翌日から起算して2年
必要書類:
故人の年金手帳・死亡診断書・埋火葬許可証
請求者としては・故人との続柄がわかる書類として『戸籍謄本』 ・『故人の住民票(除票)』および『請求者の世帯全員の住民票の写し』
請求者:故人と生計を同じくしていた遺族
申請場所:年金事務所
国民年金を納めていた人が対象で、最大32万円。実際にこれで四十九日までの費用をまかなえたご家庭もありました。

遺された家族が、生活に困らないように支給されるのが 遺族年金です。
期限:できるだけ早く、時効は5年です
必要な書類: 戸籍謄本・世帯全員の住民票・年金手帳・死亡診断書・振込先の口座情報(請求者本人名義のもの)
寡婦年金とは、国民年金に10年以上加入していた第1号被保険者である夫が 死亡した時に、夫に生計を維持されていた妻に対して、妻が60〜65歳になるまでの間、支給される年金です。 寡婦年金は名前の通り、女性に対して支給されるものです。 妻が亡くなったとしても、夫は受け取ることができません。
期限:死亡後5年以内
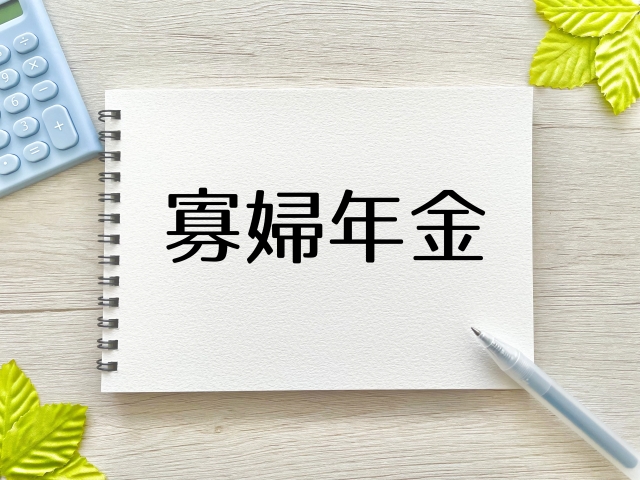
必要書類:故人の 住民票の除票・故人の死亡診断書・戸籍謄本・年金関係の書類
請求者:10年以上婚姻していた妻
請求場所:年金事務所
「夫が残してくれた最後の年金」として奥様を支える制度です。
高額療養費制度・・医療費の払い戻し
高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の1つで、医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
申請期限:医療費を支払った月の翌月初日から2年以内
必要書類:医療費の領収書・保険証・死亡診断書の写し
申請者:ご遺族
申請場所:健康保険組合や市区町村
森の風ホールで葬儀をされたご家族も「こんなに戻ってくるなんて…」と驚かれていました。

保険関連(生命保険)
期限:死亡を知った日から3年間。ただし、一部の保険会社では5年もあるため、加入している保険会社で確認しましょう。
必要書類:・死亡保険金請求書・死亡診断書・保険証券・受取人の身分証と通帳
保険会社や状況によって必要書類が異なるため、まずは契約している保険会社に連絡し、案内に従って準備を進めることが最も確実です。
申請先:保険会社
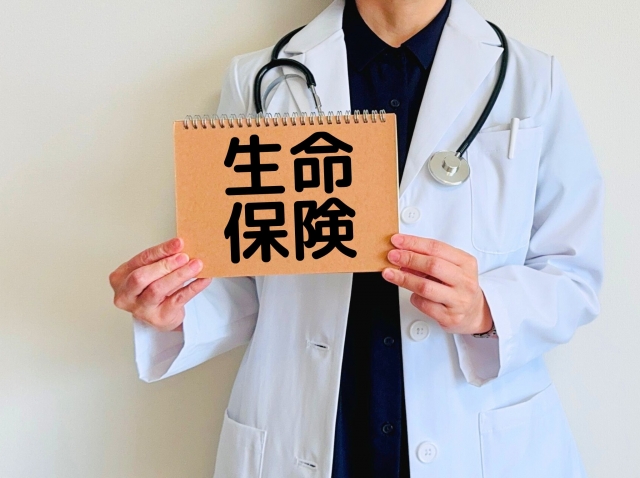
遺族補償年金・遺族補償一時金・児童扶養手当
遺族向けの手当
期限:被災者が亡くなった翌日から5年以内
必要書類:死亡診断書・労災関係の書類
申請者:配偶者や子
申請場所:労働基準監督署
遺族補償一時金とは、年金を受け取る方がいらっしゃらない場合に、配偶者、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母、などのうち最先順位者に、お支払いするものです。
期限:被災労働者が亡くなった日の翌日から5年以内
必要書類:死亡診断書など(戸籍謄本・抄本など)受給資格者全員が労災で死亡した人の収入で生計を維持していたことを証明する書類
申請者:ご遺族
申請場所:労働基準監督署
児童扶養手当とは、ひとり親家庭などが育成する子どもの生活を安定させ、自立を促進するために支給される手当です。子供を監護・養育する母、父、または養育者に対して支給されます。
申請月の翌月から支給 遡ることは不可能です。
必要書類:所得証明・死亡診断書・戸籍謄本
申請者:18歳未満の子を養育している親
申請場所:市区町村役所
森の風ホールで葬儀をされたシングルマザーのお客様も、これで子どもの進学費用を守れたと感謝されていました。
葬祭扶助制度
生活保護法に基づき自治体が最低限の葬儀費用を支給する制度です。主に生活保護受給者や故人に身寄りがいない場合に適用され、支給額は自治体によって異なり、金額は大人215,000円以内、子供172,000円以内が国の基準とされており、地域や物価によって自治体の条例で実際の支給額が決まります。
期限は 葬儀後に申請しても受理されないため、亡くなったら 速やかに福祉事務所に連絡しましょう。
申請方法は 故人の死亡後、速やかに申請者の住民票がある市区町村の役所の 福祉事務所に連絡し、葬儀前に相談します。
必要書類は 死亡診断書・故人の預貯金や遺族の経済状況を確認するための資料が必要になる場合があります。
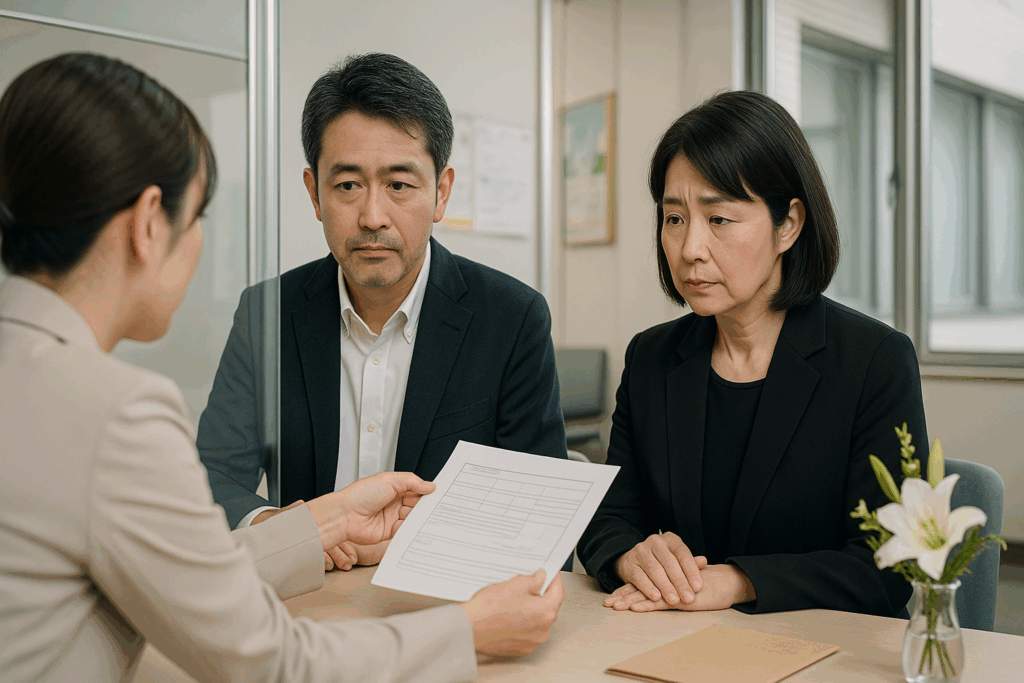
福祉事務所に申請書類を提出し、経済的な状況などを調査・審査してもらいます。
故人に十分な資産がある場合や、遺族に葬儀費用を負担する経済的余裕があると判断された場合は、制度の対象外となることがあります。
審査の結果、葬祭扶助の適用が決定したら、葬儀社に「葬祭扶助で葬儀を行いたい」と伝えて依頼します。
葬儀社が福祉事務所に直接葬儀費用を請求し、支払われます。
今日お伝えしたのは 亡くなったらもらえるお金です。でも大切なのは、申請しなければ一円も受け取れないという現実です。
葬儀の負担を少しでも軽くすること、その後の暮らしを守ること。これは“知識”という形の供養だと私は思います。私たち多摩中央葬祭・森の風ホールでは、葬儀そのものだけでなく、こうした手続きや書類整理も含めて、サポートしております。ご家族に安心をお届けしたい…と考えております。
形よりも気持ち。無理なく備えることが、いちばんの供養につながります。この記事の内容をぜひ保存して、ご家族と共有していただけれ幸いです。

 0120-136-841
0120-136-841