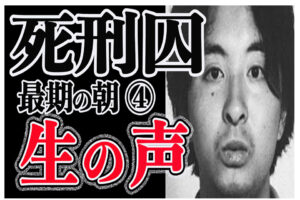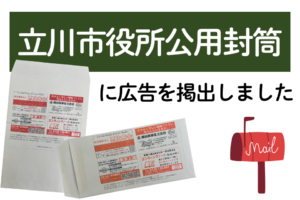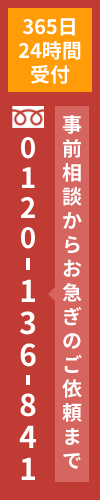「親の 死に目に会えないのは 最大の親不孝だ・・・」そう言われて育った人、多いのではないでしょうか。 だから“危篤”の知らせが届いた瞬間、仕事も家族も全部放り出して 駆けつけなきゃ…と 体が勝手に動く。
でも…現実はいつも間に合うとは限りません。
「あと5分早ければ…」
「あの時、仕事を抜ければよかった…」
そんな悔しさを、何年も抱え続けている人を、私はご葬儀で数えきれないほどみてきました。けれど 本当にそれは“親不孝”なのでしょうか?
「死に目に会えなかった・・・」
「あのとき○○していれば・・・」などと 本当にアナタだけの せいだったでしょうか?そのときに 何かしていたら、変わっていたでしょうか?
本日の記事では 医師や看護師、そして遺族の声から見えてくるのは、実は まったく違う真実なんです。コレらの 誤解を解き、あなたの後悔という重荷を、少しずつおろしていく方法をお伝えします。

死に目に会えなかった後悔・・・
大切な人の最期に立ち会えなかった・・これ本当に言葉にするのも辛く、そんな後悔に胸が締め付けられた経験 ・アナタはありませんか?・・
でも、もし今アナタがそういう気持ちを抱いているなら、決して1人じゃないんです。これYahoo知恵袋にあった ある方の心の叫びなんですけども、大好きな人が亡くなりました。死に目に会えませんでした。
胸が苦しくて痛いです。こんな時は どうしたらいいのでしょうか?

または大切な人の死んだ姿を見たくない気持ちと、ちゃんと見送りたい気持ちで 胸が苦しい… どうしたらいいか?と 投稿されています。
んーこの言葉 本当に胸が締め付けられます。すごく人間らしくて、誰もが わかるよ。。。って言う痛みだと私は思うのです。
特に日本だと この感覚 より一層強いと思います。親が危篤との報せが入ると、どんなに忙しくても、取るものもとりあえず 駆けつけるのが当たり前ですし、世間もそれを当然のように 受けとめています。
こういう社会的なプレッシャーが 後悔をもっともっと 深くしているという側面があると思います。でも皆さん、ここでちょっと視点を変えて見て欲しいんです。
この言葉の本当の意味は、「親よりも先に死ぬことが最大の親不孝」ということのようです。「親の死に目に会えない」というのは、実際に親が死に瀕しているときの話ではなく、自分が親より先に死んでしまうことを言っているのだそうです。
死に目の定義と誤解
ーー医学的な死の瞬間・死の定義ーー
私たちが死の瞬間と呼んでいるもの…これ 実は医学的に はっきりとした基準があるんです。医者が法的に死亡を判断するためのもので、それが この死の3懲候と呼ばれているものです。
1つ目 呼吸が止まっていること
2つ目 心臓の鼓動が完全に停止していること
3つ目 瞳孔が開いていて 光を当てても何の反応も示さないこと

医師はこれら3つを全部確認して、医学的に亡くなりました、、と判断するわけなんです。私たちは人の 死って言うのは 医師の 亡くなりました、、、と言う時。。ロボットのスイッチをパチっと切るように突然訪れるものだと思っていますが、本当は違うんです。
医学的な現実は、段々と機能が止まっていくプロセスなんです。命の光がパッと消えるのではなく 徐々にフェードアウトしていく、、、そんなイメージが正しいのです。
1,000人以上の方の最期を看取ってきた看護士の ごかん めぐみ さんは こう言っています。
呼吸が止まって 直ぐに全ての細胞が死んでしまうわけではないので、そのわずかに残された『生』の部分が、『ぬくもり』として残されています。
つまり息が止まった後でも まだ体には温かみが残っている。そのぬくもりこそが、大切な方との繋がりが、まだそこにあるっていう証拠なのかもしれません。
医師による死亡確認は あくまで法律上の社会的な区切りとして、必要なことなんです。でも、それが生物学的に 全てが終わりってわけじゃないんです。
細胞のレベルで見れば 命の活動はまだ しばらく続いている、、と おっしゃています。この事実を知るだけでも あの瞬間に居なきゃいけなかった、、、っていう一点にかかる重圧が、少しだけ軽くなるような気がしませんか?
死が 『点』じゃなくて、ある程度の幅を持ったプロセスならば、じゃあ 私たちが云う『見送る』っていう行為そのものの意味も、実は もっと広いものではないでしょうか?
最期の看取り・お見送りの真の重要性とは
そこで出てくるのが この『看取り』と云う言葉の新しい捉え方・新い考え方なんです。ご葬儀でいう、お別れ。。。という考え方なんですが、看取りっていうと どうしても死の瞬間に立ち会うこと、、というイメージが強いと思いますが、でも そうじゃないんです。
新い考え方としては それまでのケア、、、とか お別れの気持ち、、、とか その人が旅立つまでの道のり全部をひっくるめた もっともっと大きな概念だと 云うのです。
これら看取りの実際のエピソードです。
あるエッセイストのお話です。彼女が病院に到着した時は、お母さんが息を引き取った後でした。当然 自分を責めますよね…そんな彼女にお父さんがこう言ったんです。『ただ死ぬ瞬間に そこに居なかっただけのことだ、気に止む必要はない』 この一言で彼女の心は 少し救われたんです。
そして彼女はハッと気づくんです。『あー本当のお別れって あの病院の一瞬だけじゃなかったんだな…亡くなる少し前に親子で出かけた旅行、あのかけがえのない楽しい時間こそが、自分にとっての本当の看取りであり、ちゃんとしたお別れだったんだ、、、って 』

緩和ケア医のドクタートッシュさん 先生自身もお母さんとの別れで 全く同じような経験をしています。先生はお母さんが危篤だって知らせを受けて、4時間かけて車を運転し 駆けつけたそうです。その運転中 頭の中は、お母さんとの小さい頃からの思い出でから始まり いっぱいだった、、、と。でも施設に着いて、そばに付き添っていたにも関わらず、お母さんが息を引き取った まさにその時、先生は隣の椅子で うたた寝してしまっていたそうです。でも それを 先生は後悔していないそうです。
なぜなら彼にとって 本当の看取りとは、その瞬間じゃなかったから…お母さんのことだけ考えて車を走らせた あの4時間…遠く離れた場所から 母は大丈夫かな?と思った時間 。着いてから 意識がなくても お母さんの そばに居られた時間。お通夜の晩に お父さんが語ってくれた お母さんの思い出話。

そしてお葬式は家で、、、って言うお母さんの最期の願いを 叶えてあげられたこと全てが、先生にとっても かけがえのない看取りだったとおっしゃています。
この言葉はあの瞬間 立ち会えなかった多くの人にとって 本当に大きな救いになる言葉ではないでしょうか…。
つまり 大事なことは アナタの存在って言うのは 最期のたった一瞬だけではなくて、その人が生きてきた旅路全体を通して ずーと相手・亡くなった人に 伝わっていた…感じられていた…というものなんです。
お分かりだと思いますが もうアナタは確かに その大切な方を誰よりも ちゃんと見送ることができたんです。
本日のまとめ
今までの考え方 つまり 最期の瞬間が全て、、、っていう捉え方だど、立ち会えなかったことが罪悪感になってしまいます。
でも 私はこう思うのです。結局、大切なのは 関係…そのものです。
最期の瞬間に立ち会えたかどうかよりも、これまで一緒に過ごした日々、笑い合った時間、交わした言葉…それこそが本当のお別れになっていく。
その記憶は、やがて あなたの心の安らぎとなり、かけがえのない思い出へと変わっていきます。そして私は、故人も また最期の瞬間、そんな関係や思い出を胸に抱きながら、静かにあの世へ旅立っていくと信じています。
故人を想うあなたの その気持ちこそが、すでにお別れの一部、、、そう思えたとき、あなたはもう十分に大切な人を見送れているのです。
死を想うことは、今をどう生きるかを考えることでもあります。
どうか、これからの時間を後悔なく、夢中で生きてください…それこそが、故人が一番喜ぶ “生き方の贈り物”になると私は信じています。

 0120-136-841
0120-136-841